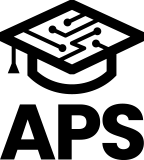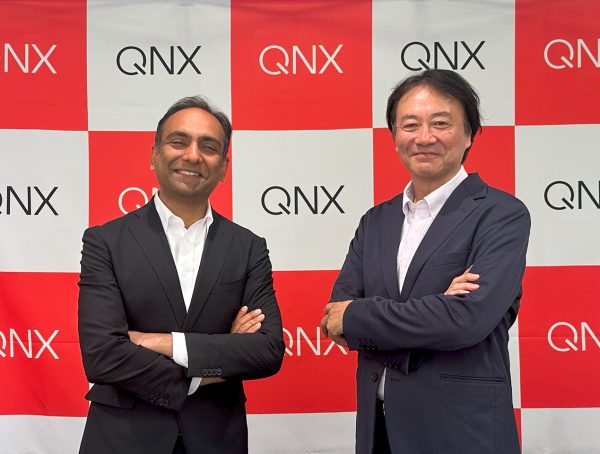センサーを利用した新たな製品やサービスが増えてきた。「ウェアラブル・コンピューティング」や「センサー・アプリケーション」といった新たな製品セグメントもできつつある中、今回ご紹介するのが、ドリームフォレスト社が開発したモーションセンサー「MyMo」だ。STマイクロエレクトロニクス(以下、ST)のMEMSセンサーとArmマイコンを組み合わせて、ゴルファーのスイングを丸裸にするユニークな製品である。同社の𠮷田雅信社長に開発の経緯などを聞いた。
ゴルフスイングを解析するモーションセンサーを開発
本日はドリームフォレストの𠮷田社長をお招きして、同社が開発した「MyMo」(マイモ)というゴルファー向けのモーションセンサーについてお聞きしたいと思います。まず始めにドリームフォレストの概要を教えてください。
ドリームフォレスト 𠮷田:僕は以前ソニーにいて、スマホの前身に相当する「Clie」(クリエ)というPDA(パーソナル・デジタル・アシスタンス)事業を担当していたんです。その後2007年にソフトバンクに移ってiPhoneの導入などを手がけてきました。コンピュータの歴史はメインフレームがパソコンになり、PDAになり、さらにスマホへと変遷してきたわけですけど、その本質は「(コンピュータが)遠いところから近いところへやってくる」にあると考えたんですね。そうすると次はウェアラブルのような世界が当たり前になるだろうと。いろいろなデータを集めるセンサー、そのデータを集めて処理をするスマホ、それによって付加価値を生むクラウド、という三つのレイヤーを組み合わせた製品やビジネスモデルを作る会社として、2011年の年末にドリームフォレストを創業したんです。
最初の製品としてゴルファー向けのワイヤレスモーションセンサーを開発されました。
ドリームフォレスト 𠮷田:ゴルフっていちばん注目してもらいやすいんですよ。競技人口も多くて、日本に1000万人、アメリカに3000万人いると言われてますし、用具にお金も使ってくれます。それに、球がまっすぐ飛ばないんだけど、みたいに話も弾むじゃないですか。じゃあまずはドリームフォレストが目指す事業のプロトタイプとして、スマホやクラウドとの連携も考えて、ゴルフのスイングモーションをキャプチャするセンサーを作ろうじゃないかと。そうやって製品作りを考えていったとき、いろいろなデバイスを探している中で、STとのお付き合いが生まれてきたんです。
そこの経緯をもう少し詳しくお願いします。
ドリームフォレスト 𠮷田:ゴルフのスイングをセンシングしようとすると加速度センサーと角速度センサー(ジャイロ)がどうしても必要で、それをやっている半導体ベンダーは世界でもそんなにないんです。両方やっていて、なおかつシステムとしてお付き合いできるところを探していくと、STがベストだろうと判断しました。
ST田辺:ドリームフォレスト様のようなベンチャー企業からのお問い合わせは、STに入社してから初めての経験でしたが、とても興味深いビジネスだと思いました。「MyMo」の開発では技術的なサポートを含めて全面的に協力させていただいております。なお、加速度センサーや角速度センサーなど、当社のMEMSセンサーデバイスはスマホやゲーム機に採用されるなどワールドワイドで高いシェアを誇っていますので、性能と実績ともに自信を持って提案させていただきました。当社のデバイスを選定していただき、とてもありがたく感じています。
センサーデバイスと一緒にArmマイコンを採用されたと。
ドリームフォレスト 𠮷田:センサーデバイスが出力する生のデータってそのままアプリには渡せなくて、データを動き量に変換してやらないといけないんですが、STはセンサー出力を処理する「iNEMOエンジン用ソフトウェアライブラリ」を提供してくれてるんですね。製品には結局は組み込まなかったんですけど、開発段階はそういうライブラリがないと大変なので、その点はSTのArmマイコンを選定した大きな理由のひとつでした。なお、マイコンにはCortex-M3プロセッサベースの「STM32F103」を採用しています。
ST塩川:Armマイコンを提供している半導体ベンダーはすでに10社を超えていますが、STではお客様の開発がスムーズに進むように、ドリームフォレスト様が使われた「iNEMOエンジン用ソフトウェアライブラリ」をはじめとして、さまざまなファームウェアを用意しています。そこはSTの優位性のひとつだと思っています。
ST立薗:STでは「センサー・フュージョン」という呼び方をしていますが、マーケットからの要求も増えていることもあって、モバイル機器でのセンサー処理用途を想定したポートフォリオを積極的に展開していこうとしています。センサー、Armマイコン、そして関連のファームウェアおよびライブラリをワンストップで提供できる総合力は、確実にSTの強みのひとつですね。
9軸データを毎秒500サンプル。徹底的な軽量化で10g台前半を実現
実際の設計では、大きさ、重さ、バッテリ動作時間、耐衝撃性など、さまざまな要件や課題があったかと思います。
ドリームフォレスト 𠮷田:ソニーの社長・会長を歴任して今はドリームフォレストの役員をやっている出井伸之はゴルフが大好きなんですが、最初に「MyMo」の構想を話したときにものすごい拒否反応を示すんです。ゴルフは好きだし、ガジェット系は大好きだし、なんでって訊いたら、クラブに1グラムも付けるのは嫌だって言うわけですよ。ところが、いろいろな人にヒアリングしてみると、スコアが100を切れないようなゴルファーは欲しいって答えるわけです。じゃあターゲットをどちらに絞りますかっていったら、ゴルファー人口のピラミッドのうち、スコアが伸びずに困っている95%の人たちをターゲットにしようと。ただ、5%の人たちから「あんなオモチャ」ってバカにされるようなものを出すと、本来の95%の人たちも買ってくれなくなるので、とにかく重さにはこだわりました。カタログには15グラムって書きましたけど、実力としては13グラムを達成しています。
バッテリ容量と動作時間のバランスも難しそうですね。
ドリームフォレスト 𠮷田:軽くしようとするといろいろなところで妥協しないといけなくて、いちばんは電池なんです。ゴルフのラウンドを考えると4時間から5時間は動いて欲しいので、あとはいかに省電力で回路を設計するかっていうところですよね。ソニーでClieを作りましたし、その前にはハンディカムも担当していたんで、ソニー時代に教わった小型軽量化や省電力化の経験は自分にとっての大きな財産ですね。
ST塩川:消費電力をいかに抑えるかというのは、あらゆる組み込み機器で課題のひとつになっているかと思います。Armマイコンでいうと、たとえばRUNモードでの消費電力はA社製品のほうが優れていて、SLEEPモードでの消費電力はB社製品のほうが優れている、といったことは実際にあるのですが、実際のシステムでそれらを組み合わせたときの実効的な消費電力でみるとSTの製品が優れているとの評価をいただいております。マイコンの選定のときにはカタログ値だけでなく、そうした尺度で評価していただきたいと、お客様にはご紹介しています。
STにはローパワーの「STM32L」というマイコンファミリもあります。
ドリームフォレスト 𠮷田:スイングのセンシングって大変で、加速度センサー3軸と角速度センサー3軸を毎秒500サンプルで捕まえないと、ドライバーのヘッドの軌跡を捉えられないんですよ。そうすると動作周波数の低いローパワーマイコンでは処理が追いつかなくて、「STM32F103」でギリギリだろうという判断で選定したんですね。
ST塩川:「STM32L」というローパワー製品の周波数は最高32MHzですが、「MyMo」では「STM32F103」を72MHzで動かしておられますね。
ST立薗:STでは、センサーデバイスとArmマイコンの組み合わせ強化の一環で、Arm Cortex-M4コアを搭載した「STM32F401」という製品ラインの展開にも力を入れています。「STM32F401」はセンサー・アプリケーションに特化したArmマイコンで、ペリフェラルなどは、あえて最低限のものしか積んでいません。また、本来「STM32F4」シリーズは180MHz動作などハイパフォーマンスを狙った製品ラインなんですが、「STM32F401」は最高周波数を84MHzに落としていますので、消費電力の点でも有利かと思います。今後はそういったご提案をさせていただければと考えています。
新たなマーケットを活性化するセンサー中心のエコシステム
センサー・アプリケーションを開発するにあたって課題があれば教えてください。
ドリームフォレスト 𠮷田:センサーを中心にしたエコシステムってまだ不十分なんですよ。センサーを使いこなそうとすると、それぞれのセンサーのクセを理解したうえで出力値を物理量に変換しなければいけないわけですけど、先ほど触れた「iNEMO」だけではなく、SDKやライブラリがもっと整備されればアプリが簡単に書けますから、そういう情報やリソースを草の根レベルにまで開放してもらえると有難いので、STにはぜひセンサー・エコシステムを作ってもらいたいと思いますね。
ST立薗:マイコンのエコシステムはそれなりに整備してきたつもりですが、𠮷田様がおっしゃられたセンサーを中心にしたエコシステムは、課題のひとつとして捉えています。一部、角速度センサーなどを搭載した「STM32F3」シリーズの評価ボードや、先ほど触れた「STM32F401」の評価ボードがあるぐらいでしょうか。このご指摘はとても重要なことですので、前向きに検討させていただきます。
実際にモノを出したあとの市場の反応はいかがですか?
ドリームフォレスト 𠮷田:株式会社アクセスから「Fullmiere」(フルミエル)という製品名で、2013年1月からAndroid用を、2013年7月からはiPhone用を販売していますが、多くのレベルのゴルファーの皆さんから「こんなツール今まで見たこともなかった」という感想が多く寄せられています。それに、シングルやプロのゴルファーも、実際のモノを見せると、「結構軽くて問題ない」と評価してくれているんで、まぁ良かったかなと。
冒頭でクラウドというお話もありましたが、どういったビジネスモデルを描いているのでしょうか?
ドリームフォレスト 𠮷田:第一ステップとしてはまずは物販ですね。最初からクラウドのサービスを狙っても、ある程度のクリティカルマス(数量)を超えないとビジネスモデルが成り立ちませんので。
ゴルフに限らずさまざまなスポーツに応用ができそうですね。
ST立薗:私もそれは思っていて、どのタイミングで言い出そうかと(笑)。私はランニングを趣味でやっていて市民レースにも頻繁に出場しているのですが、両足にこうしたセンサーを付けてフォームのバランスなどをチェックできたら面白いなと思います。ランニング人口も日本に1000万人はいるとのデータがあるようです。
ドリームフォレスト 𠮷田:ゴルフは毎秒500サンプリングが必要ですが、ランニングだったらもっと粗いサンプリングで済むので、バッテリも長持ちするかもしれません。アプリのプロトタイプさえ作ってくれる人がいればすぐに製品化できると思います。
ST田辺:テニスのラケットに装着してスイングを解析するなどのアイディアもありそうですね。STとしても、今回を成功事例のひとつと捉え、今後力を入れていこうとしている「センサー・フュージョン」を新しいアプリケーションの提案につなげていければ嬉しく思います。
最後に今後のビジョンをお聞かせください。
ドリームフォレスト 𠮷田:ウェアラブルのような製品やビジネスモデルがこれからどんどん出てくると思うんですが、開発コストの高い大企業じゃ無理だと思っていて、うちのようなベンチャーがどうチャレンジしていくかなんですよね。先ほどもお願いしましたけど、STにはセンサーのエコシステムを作ってもらいたいなと。当社を含めてみんなが参入しやすくなりますし、そういう環境を整備した半導体ベンダーだけが勝ち残ると思っています。
大変興味深いお話をありがとうございました。
こちらも是非
“もっと見る” インタビュー
パナソニックが電動アシスト自転車にSTM32を採用。タイヤの空気圧低下をエッジAIがお知らせ
国内の電動アシスト自転車市場で圧倒的なシェアを誇るパナソニック サイクルテック。同社が新たに開発したのが、タイヤの空気圧低下をAIで推定する「空気入れタイミングお知らせ機能」である。パンクの原因にもなる空気圧低下を乗り手に知らせて、安全性と快適性を高めるのが狙いだ。アシスト用モーターの制御とAIモデルの実行にはSTのSTM32マイコンを採用した。開発の経緯や仕組みについて話を聞いた。
顔認証端末「Noqtoa」の高性能を支えるi.MX 8M Plusプロセッサ~内蔵NPUが0.2秒のレスポンスを実現~
NXP Semiconductorsのi.MX 8M Plusアプリケーション・プロセッサとサイバーリンクのAI顔認証エンジンFaceMeで構成した宮川製作所の顔認証端末「Noqtoa(ノクトア)」。i.MX 8M Plusの特徴のひとつであるNPU(ニューラル・プロセッシング・ユニット)を活用して、人物の顔の特徴量抽出を高速化し、1万人の登録に対してわずか0.2秒という顔認証レスポンスを実現した。宮川製作所で開発を担当したお二人を中心に話を聞いた。
ウインドリバーが始めた、Yocto Linuxにも対応する組み込みLinux開発・運用支援サービスとは?
リアルタイムOSの「VxWorks」やYocto Projectベースの商用組み込みLinuxである「Wind River Linux」を提供し、組み込みOS市場をリードするウインドリバー。同社が新たに注力しているのが組み込みLinuxプラットフォームソリューションの開発と運用の負担を軽減するLinux開発・運用支援サービスの「Wind River Studio Linux Services」だ。